
Kenji Fukushima (福島 健児)
@kfuku0502
A researcher getting trapped by carnivorous plants
ID: 4514679019
https://sites.google.com/site/kfuku52/ 10-12-2015 05:10:35
9,9K Tweet
3,3K Followers
1,1K Following

I’m happy to inform that our gall paper is now open in Plant Direct Journal. Parasitic‐Plant Parasite Rewires Flowering Pathways to Induce Stem‐Derived Galls - 2025 - onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pl…


New preprint ! - “Complexity and Innovation in Carnivorous Plant Genomes” - a review paper on carnivorous plant genomes: zenodo.org/records/169361… #drosera #Nepenthes #utricularia #carnivorousplants #genomics #evolution Kenji Fukushima (福島 健児) André Marques: co-corresponding authors

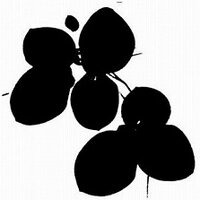


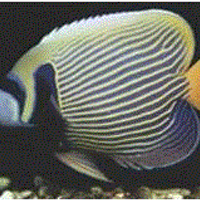

Excited to share our new paper in Nature Communications! We discovered a molecular morphological convergence: distinct alcohol-aldehyde dehydrogenases independently evolved similar homomeric complexes. See threads for a brief introduction. Paper: doi.org/10.1038/s41467…











